こんにちは!ayaです!
いつもお手に取っていただき
ありがとうございます。
今回はずっと触れるかどうか迷っていた
“虐待“についてお話していこうと思います。
私は幼少期、母が少し育児ノイローゼ気味でしたが、今振り返れば愛されて育った方だと思います。
なので「虐待」という言葉をはじめて知ったのは
小学校の図書館で借りた
『“it”と呼ばれた子』を読んだ時でした。
ガスコンロで焼かれる。塩酸入り洗剤で掃除をさせられる。赤ん坊の汚物を食べさせられる。児童虐待を生き抜いた著書がはじめて明かした、壮絶な日々の記録。
「なぜ、ぼくだけがこんな目に?」———母親に名前さえ呼んでもらえない。“That Boy(あの子)”から、ついには“It(それ)”と呼ばれるようになる。
食べ物も与えられず、奴隷のように働かされる。身の回りの世話はおろか、暴力をふるわれ、命の危険にさらされ、かばってくれた父親も姿を消してしまう———
本書は、米国カリフォルニア州史上最悪といわれた虐待を生き抜いた著者が、幼児期のトラウマを乗り越えて自らつづった、貴重な真実の記録である。
この本を読んだ時、はじめて本を読んで
嘔吐したのを覚えています。
世界のどこかにこんな生活を強いられている子どもがいることが信じられませんでした。
ノンフィクションだけどこれは「海外のお話」と思っていたのも儚い夢で、
昨今どんどん取り上げられる虐待死のニュースに、本当に行き場のない思いが募るばかりです。
そして、保育士になった現在「虐待」はより身近なものになりました。
「あのね、ママが私のこと「ゴミだから」って置いてっちゃったの。しばらくしたら拾いに来てくれたよ!優しいでしょう??」
そうキラキラ目を輝かせて言う女の子に
出会ったことがあります。
前々から少し「荷物の整理が苦手な子だなぁ」と思っていました。
半年以上分の塗り絵や制作物がカバンに入ったままで、お弁当の湿気でカバンの底はカビて異臭を放っていました。
ママもはじめのうちはあまり目が合わず、ケータイばかり見ている印象でしたが少しずつ心を開いてくれたのか
「先生のエプロンかわいいですね」など連絡事項以外の会話もしてくれるようになっていたので
「良かった〜」と安心していた最中での
その発言に本当に戸惑い、
かける言葉が見つからず「そっか」とだけ返しました。
先輩にも相談しましたが目立ったアザもなく、保育所にも毎日通えているという観点から「経過観察」にとどまりました。
保護者支援も担う私たちにとって「疑う」という行為は信頼関係を崩す可能性が大いにあります。
子どもを守ることと大人を守ること両方の均衡を保った支援の難しさを保育士になり、ひしひしと感じています。
さて、「虐待」と言ってもいくつか種類があることは教育関係者の皆様なら周知の事実かと思いますが、改めて述べさせていただきたいと思います。
①身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
②性的虐待
児童にわいせつな行為をすること、又は児童にさせること
②性的虐待
児童にわいせつな行為をすること、又は児童にさせること
(例
※児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、又は長時間の放置
※保護者以外の同居人による虐待行為の放置
④心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(例
※児童に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な態度※児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力
以上の4つが虐待の種類になります。
この中で、近年1番多く行われているのが心理的虐待です。
令和4年度、こども家庭庁の調査によると相談の内容別件数は多い順に
心理的虐待 12万9,484件(全体の59.1%)
身体的虐待 5万1,679件(23.6%)
ネグレクト 3万5,556件(16.2%)
性的虐待 2,451件(1.1%)
となっています。
身体的虐待やネグレクトはアザや持ち物など目に見えて分かりやすいですが
心理的虐待は「各家庭の子育て観」と
言われてしまえば、私たち保育士は
それ以上踏み込むことは難しくなりますし、
そもそも、その話題に保護者様に面と向かって話すことはとっても勇気がいりますよね。
ここでひとつ覚えておいてほしいのは
子どもも大人も「虐待」「被虐待」の意識がほぼないということです。
「虐待をしてやろう」という犯罪者的な思考については分かりませんが
保育所に通われる保護者の方はどうしようもない経済状況や行き場のない気持ちが、立場的にも身体的にも弱い子どもに
出てしまっているだけな気がします。
もちろん子どもは、愛されたいと願うので親を悪く言う子に出会ったことは、ほぼありません。
むしろ、家庭環境が安定している子の方が
「パパの髪型が変だ」とか
「ママの体型がどうだ」とか
そんな話をする印象です。
「保護者にも理由がある」と言っても
やはり虐待を容認するわけにはいきません。
私たちは警察でも児童相談所でもないため物理的にできることはほぼありません。
こんなに子どもに関わる仕事なのに「保護者支援」「信頼関係構築」に気を取られて通告義務の基準もどんどん低下しているように思います。
そんな中で私達が子どものためにできることは「気づく」ことです。
それでは、どのような部分に焦点を当てて気づきを得ればいいのか?
についてお話しようと思います。
1.身体
まずは、目に見えてわかる部分から
注目してください。
私たちは日々、健康観察や着替えなど
子どもの身体を見たり触れたりする機会が多いですね。
その時に、
「アザはないか」
「触れて痛がる様子はないか」
「大きな怪我が放置されている形跡はないか」
などよく観察してみてください。
2.持ち物
次に目に見える事項として「持ち物」があげられます。
「忘れ物が著しく多い」
「服や靴がカビている、穴が空いている」
「保育所で汚れた服が洗濯されていない」
「制作物やおたよりなどがカバンにずっと入ったまま」
など、持ち物からも異変を感じることができます。
3.保護者の関わり方
送迎時の様子からも気づくことが多いです。
「子どもに冷たく当たる」
「兄弟間で関わり方に差がある」
「子どもと目を合わせない」
「ペットを愛でるように扱う」
「携帯ばかり見ている」
など、保護者様にも注意してみてください。
4.保育士への関わり方
子どもが保育士に対してどう関わるかも
大事なポイントです。
「著しく執着する、又は全く近づかない」
「大きな声や音を怖がる」
「他の子を叱ると一緒になって怯える」
「何でもかんでも保育士に確認を取る」
多数の子を見ているからこそ気付けることがあります。
5.三代欲求
わたしが先輩から聞いて「なるほど」と思ったのがこの部分です。
人間にとって「愛されたい」という欲求は二次欲求で、成長と共に芽生えるものです。
そして、幼少期はほぼ満たされている子
ばかりなのですが、そこが満ちておらず
本能的に「愛して!」と子ども達が訴える方法は
「食欲」「睡眠欲」「性欲」
の一次欲求に現れると言います。
食欲
「食べ物を見ると目を光らせて飛びつく」
「自分の分がなくなると泣き暴れて訴える」
「詰め込み食べをして嘔吐する」
「満腹中枢が働かず際限なく食べる」
睡眠欲
「昼寝をしない、又は眠り続ける」
「極端なショートスリーパー」
性欲
「自慰行為が見られる」
「裸を見られることを喜ぶ」
など本能的な部分が著しくおかしい時も
注目した方が良いそうです。
「なんか今日はいつもと雰囲気が違うな」
「いつもより行動範囲が狭い気がするな」
この“いつもと比べて”という観点は
保育士にしかない強みです。
目に見えない“心“に気づくための貴重な材料を私たちは日々拾っています。
そのセンサーをフルに働かせて穏やかに笑う子どもの異変にどうか気づいてください。
これまで、
雪の中、靴を履かずに買い物について来ている子
レジ前の商品を漁って母のバックに入れる子(母は特に謝罪や叱咤なし)
休み連絡がなく、昼頃1人でパジャマで登園した子(近所の方が園名を聞き出し連れて来てくれました。)
など園内外問わず様々な状況を目にして来ました。
「おや?」と感じつつも
「親と一緒にいるし…」
「一応迎えに来るし…」
と、一歩踏み出せないことに滞りを感じていました。
今でもすぐに動き出せるかと言われれば
デリケートな問題なので難しい所ではあるのですが
気付いたことを園内でアウトプットしてみる
これだけで状況が動くきっかけになるかもしれません。
当たり前の話をしますが、ほとんどの子は親子関係も良好で心から「パパママ大好き」で育っています。
ただ、その中だからこそ
なかなか言い出せない子
おかしいと気付けない子
が少数ではありますが、存在している事も決して忘れないでください。
虐待に関する相談件数は年々増加傾向にあります。
児童相談所も警察沙汰になるまで
家庭に踏み込めないのが現状です。
「子どもが保育所に来なくなったら
教えてください」
この言葉を幾度も相談員の方から聞いてきました。
本当に来なくなってからの援助でいいのか?
もっと各機関と協力できることはないのか?
第2の家庭と呼ばれる保育所で
私たちが子どものためにできることは何か?
色々な観点から見つめ直してほしいという気持ちを込めて
今回は心が痛む題材をあえて取り上げさせていただきました。
子ども達が変に大人に気を遣わなくてもいいように
子どもに大人の機嫌を取らせなくても良いように
のびのび笑える場を提供できるように
そんな環境が増える事を願って…
最後までお読みいただき
ありがとうございました。

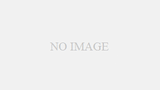
コメント